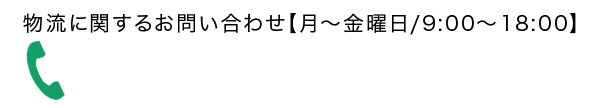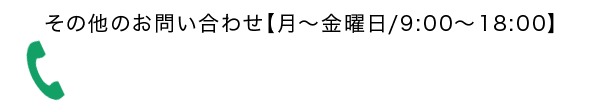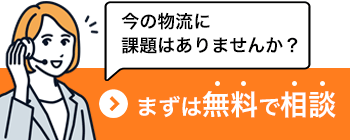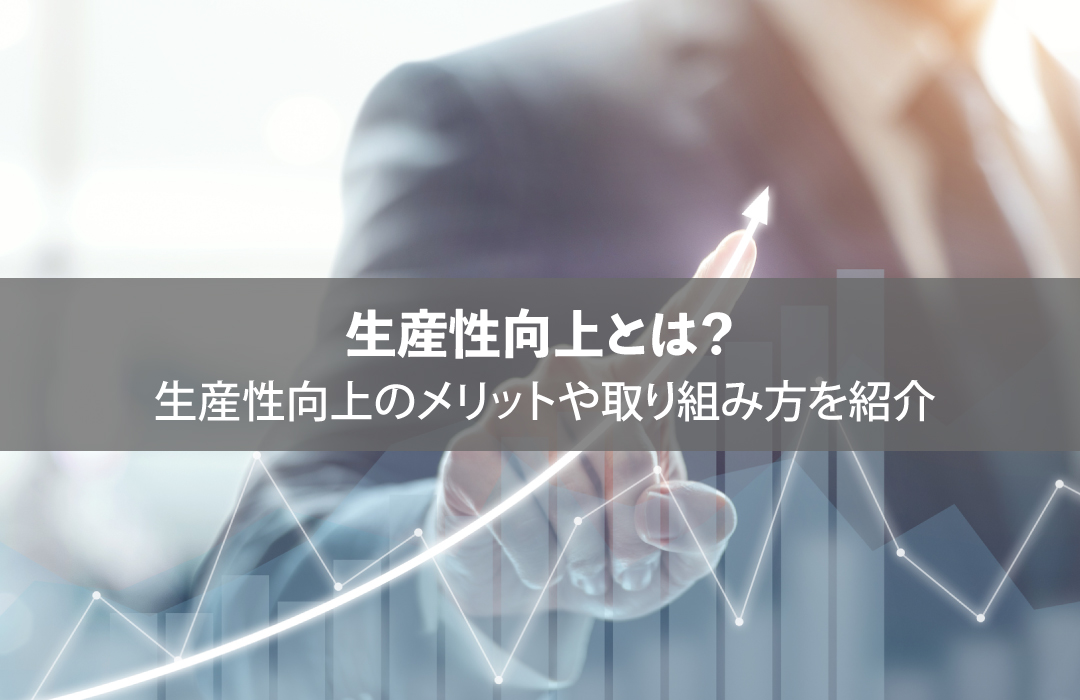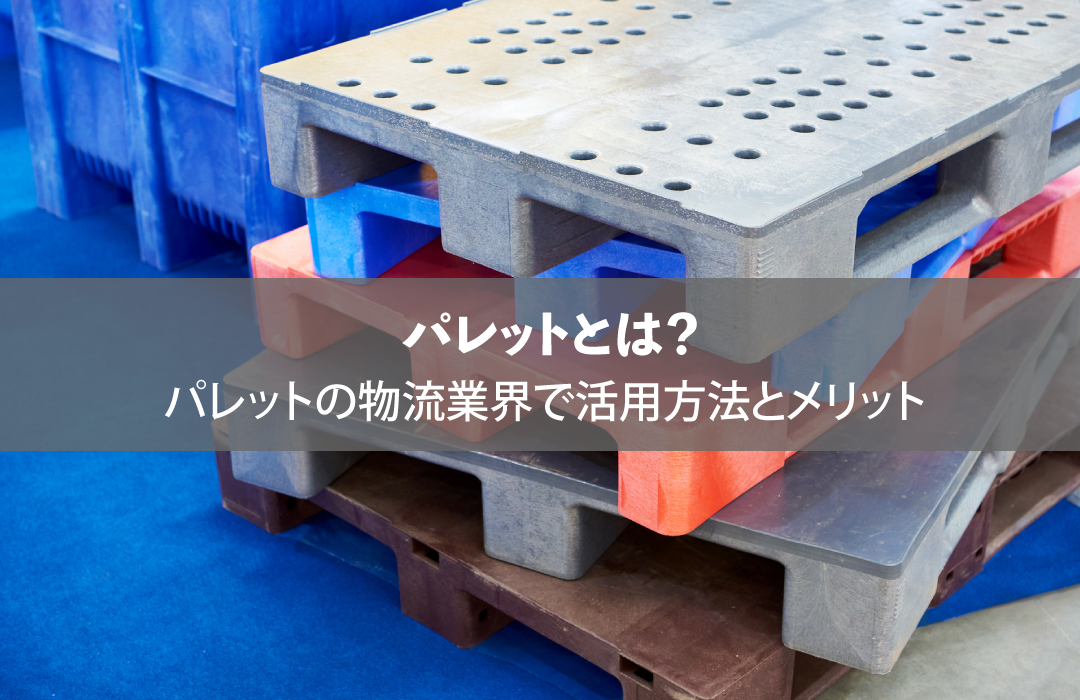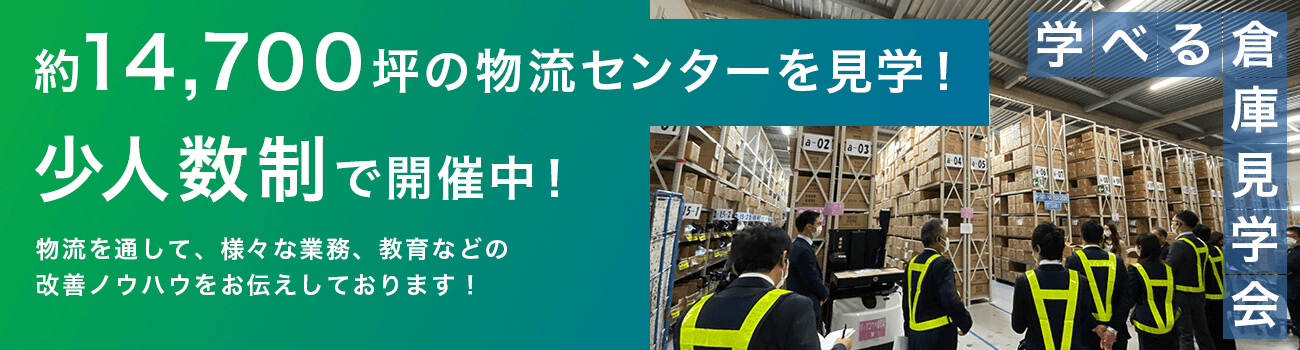在庫管理とは?|在庫管理の重要性とメリット
在庫管理とは、企業や組織が商品、材料、製品、部品などの物品(在庫)の
保有・管理を効率的に行うためのプロセスや活動のことを指します。
在庫管理は、仕入れや売上、様々なものに直結します。
ある意味で在庫管理は企業を支える土台となるものです。
この土台をないがしろにすると、企業の経営はうまくいきません。
近年、その在庫管理を行う上でバーコード管理が普及しています。
なぜなら、バーコード管理を行うことによって在庫管理が効率化されるからです。
今回はその在庫管理に対して、その重要性やメリットなどご紹介させて頂きます。
在庫管理とは

在庫管理とは一般的に、
必要な資材や商品を、必要な量を、必要な場所へ、必要なときに供給できるように
企業にあった水準で維持するための活動のことを指します。
在庫管理を英語で訳すと(Inventory control)となります。
また、管理ですので、PDCAを回すことも在庫管理の1つと言えます。
適切な計画を立て、その計画に基づき実施し、結果をチェックし、評価を行うことが
在庫管理の基本とも言えます。
▶PDCAについての詳しい記事はこちら
在庫管理をするにも、まずは何から始めればいいかお悩みの企業様必見!
「効率的な在庫管理でビジネスを強化」と題した、在庫管理の基本が学べる
ホワイトペーパーをご用意いたしました。ぜひ、ご活用ください。
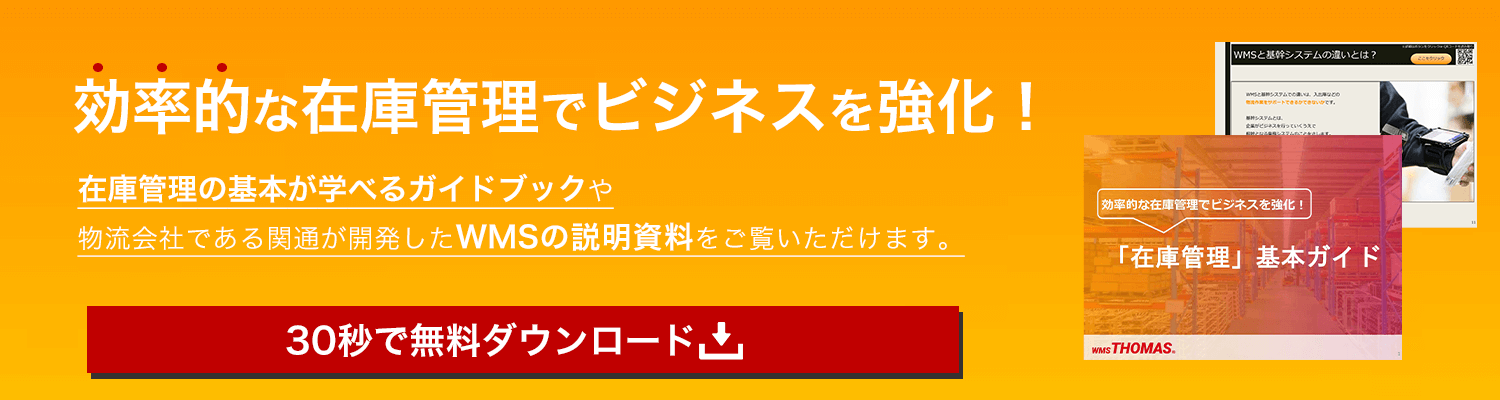
在庫管理の進め方

在庫管理の進め方は、まず、適切な在庫レベルを把握し、必要な在庫量を確保します。次に、入出庫管理や棚卸しを定期的に実施して在庫情報を正確に更新します。
また、ABC分析や在庫回転率を活用して優先順位付けを行い、重点的に管理すべきアイテムを特定します。
さらに、適切な発注手法を選択し、供給と需要をバランス良く調整します。
最後に、在庫管理システムの導入や在庫管理アプリの活用を検討し、効率的な管理を実現します。
これらの手法を組み合わせることで、在庫を最適化し、企業のコスト削減や業務効率化に貢献します。
在庫管理の方法

在庫管理の方法は、エクセルでの在庫管理表作成や在庫管理システムの活用が一般的です。
エクセルを利用すると、手軽に商品名や数量を記入して在庫を把握できますが、リアルタイム性やデータ連携が課題です。
一方、在庫管理システムは自動化された在庫情報の管理や分析を可能にし、効率的な在庫管理を実現します。
システムは入出庫情報や在庫レベルをリアルタイムで追跡し、棚卸し作業を簡素化します。
また、在庫レベルの最適化や需要予測などの機能を提供し、在庫の過不足を防ぎます。
ただし、システムの導入にはコストや学習曲線があります。
適切な方法を選択するには、企業の規模や業務ニーズを考慮する必要があります。
在庫管理の課題

在庫管理の課題は多岐にわたります。
まず、過剰な在庫は費用の増大や商品の劣化、流動性の低下を招きます。逆に、在庫不足は売り逃しや顧客の不満を引き起こします。また、手動管理では人為的なミスが生じやすく、情報の不正確性や不整合が発生します。
需要の変動や市場の変化に柔軟に対応することも難しく、競争力の低下につながります。
さらに、複数の拠点やチャネルでの在庫管理は調整が複雑化し、効率性が損なわれます。
これらの課題を解決するには、正確な需要予測や適切な在庫最適化手法、効率的な在庫管理システムの導入が必要です。
在庫管理で利益アップ

在庫管理で利益アップを図ろう!過剰な在庫は費用の増加や商品の品質低下を招き、在庫不足は売り逃しや顧客不満を引き起こします。
手動管理ではミスが生じやすく、情報の正確性や一貫性が損なわれます。
しかし、適切な在庫管理手法やシステムの導入により、これらの課題を克服できます。
需要予測の精度向上や在庫最適化を実現し、費用を削減し、効率性を高めます。
在庫管理システムの導入は情報の信頼性と可視性を向上させ、意思決定を支援します。
結果として、企業の競争力が向上し、利益の増大につながります。
在庫管理の目的と重要性

在庫管理は、企業や組織にとって非常に重要な要素です。
①コスト削減
適切な在庫管理は、在庫を最適化することでコストを削減できます。
在庫が多すぎると、保管や廃棄にかかるコストが増え、
また在庫が不足すると生産の停滞や顧客への影響が生じます。
適切な在庫レベルを維持することで、
適切な時点で適切な量を調達できるようになり、コストを最小限に抑えることができます。
②顧客満足度向上
適切な在庫管理は、顧客満足度向上にも寄与します。
在庫が適切に管理されていれば、顧客の注文に迅速かつ正確に対応できます。
製品の供給が滞ることなく、顧客の要求に応えることで、顧客の信頼を築き、
ロイヤルティを高めることができます。
③生産計画の最適化
在庫管理は、生産計画にも影響を与えます。
過剰在庫を抱えている場合、生産計画を調整する必要が生じるかもしれません。
適切な在庫レベルを維持することで、生産プロセスをより効率的に計画し、
生産ラインの停止や過度の在庫処分を回避できます。
④需要予測とリードタイムの管理
在庫管理は需要予測とリードタイム(納期)の管理と密接に関連しています。
過去の需要データや市場の変化を考慮して需給を予測し、リードタイムを考慮して在庫を調整することで、需要と供給のバランスを保つことができます。
⑤品質管理
適切な在庫管理は品質管理にも影響を与えます。
在庫が古くなったり、保管状態が悪化したりすることで、商品の品質が低下するリスクがあります。
在庫を適切にローテーションし、品質を保つことで、不良品の発生を防ぎ、企業の評判を守ることができます。
以上のように、在庫管理は企業の効率性、顧客満足度、品質管理、そして収益性に大きな影響を与える重要な要素です。
適切な在庫管理を実践することは、競争力を維持し、ビジネスの成長に貢献することにつながります。
在庫管理を効率化する方法
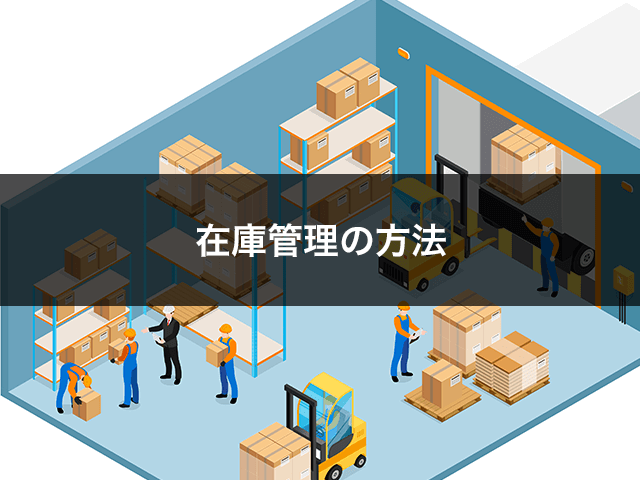
在庫管理は、企業を支える土台といえる重要な作業です。
多くの商品を正確に管理してこそお客様からの信頼を得ることができるのではないでしょうか。
それでは在庫管理の方法について説明していきます。
①在庫を把握する

まずは商品がどこに何個あるのかを分かりやすくリストアップし、
把握することが大切です。
商品は日々入庫し、出庫していきます。
そのため毎日在庫を把握する必要があります。
商品の在庫情報をしっかり管理し、把握することによって今後の販売戦略や商談を立てることができます。
アナログ管理であれば在庫のリストアップの精度は心配な部分があります。
そのため、WMS(倉庫管理システム)を用いることで、デジタル管理ができ、
リアルタイムに正しい在庫を確認することができます。
▶WMS(倉庫管理システム)ついての詳細はこちら
在庫管理を徹底解説した、「在庫管理の基本ガイド」や
物流会社である関通が開発したWMSの資料をご用意!ぜひご活用ください。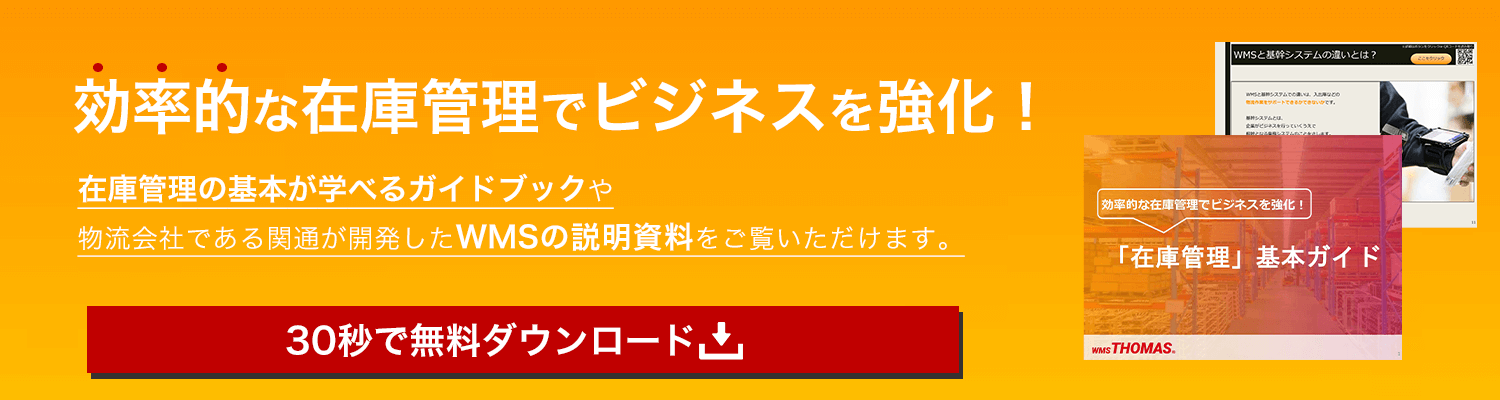
②環境を整備する

在庫管理を行う上で倉庫を清潔できれいな状態に保つことも大切になってきます。
毎日倉庫を掃除する時間を設けることによって従業員が気持ちよく作業ができると同時に、商品に埃が入ってしまうというような異物混入も防ぐことができます。
きちんと清掃された倉庫であればお客様も安心することができ、
信頼にも繋がります。
③棚を整理する

棚を整理し、管理することが大切です。
棚にはロケーションという数字をつけて管理をしましょう。
例えば、同じ分類の商品は同じ場所に固めて置くというルールを決め、
それを全員が把握し徹底します。
そうすれば間違って取ってしまった商品を元の決められた位置にすぐ戻すことができたり、商品が迷子になってしまい捜索するというような
無駄な時間を削減することができます。
④入出庫作業のルールを決める
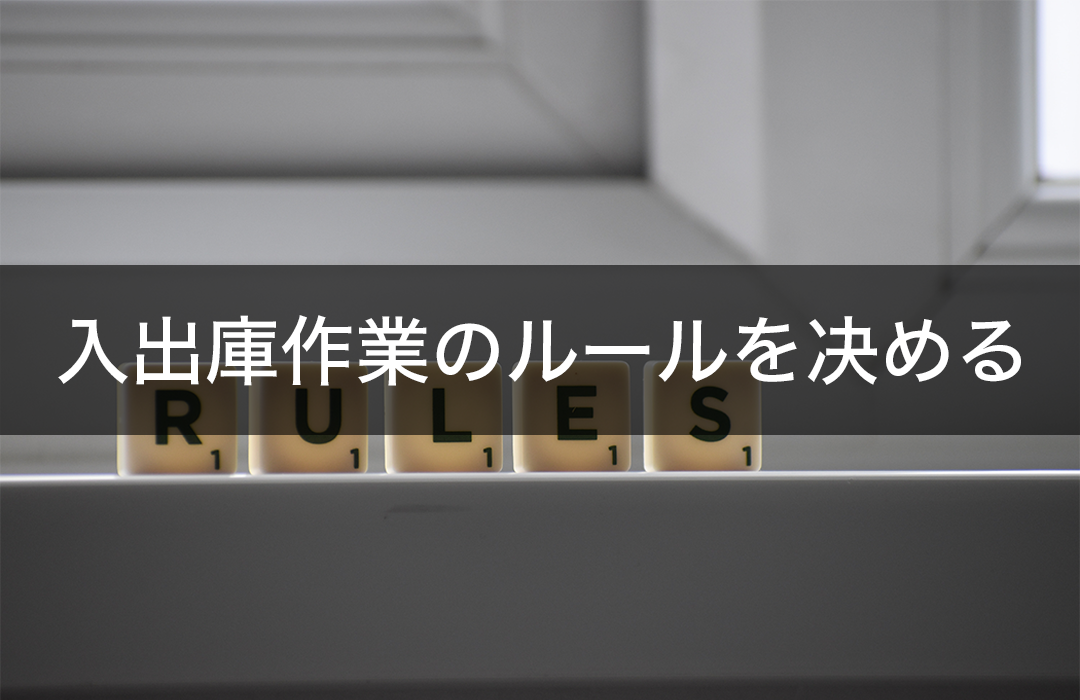
在庫や現場の環境ができても、人が間違った作業をしてしまうと在庫数は狂います。
そのため、入庫・出庫の際の作業、手順をすべて統一し、全員が共通認識のルールで仕事ができる環境を作る必要があります。
例えば、商品を棚から出庫する場合は、
手で商品を取ってからスキャンするという手順を徹底しています。
商品をスキャンしてから手で取ると、
取り間違いによる誤出荷が起こる可能性があるためです。
そのように人に手順・やってはいけないことを教育してください。
そして、実際にやらせてみて、正しく理解できているかチェックをしてください。
⑤ロケーション管理を行う
 物品や商品を保管する場所を効果的に管理し、追跡するためのプロセスや戦略です。特に倉庫や物流センターなどの施設において重要な役割を果たします。
物品や商品を保管する場所を効果的に管理し、追跡するためのプロセスや戦略です。特に倉庫や物流センターなどの施設において重要な役割を果たします。
正確なロケーション情報を持つことで、在庫の取り扱い、ピッキング、追跡、
保管効率の向上などが可能となります。
ロケーション管理についての詳細は、こちらからご覧いただけます。
⑥ABC分析
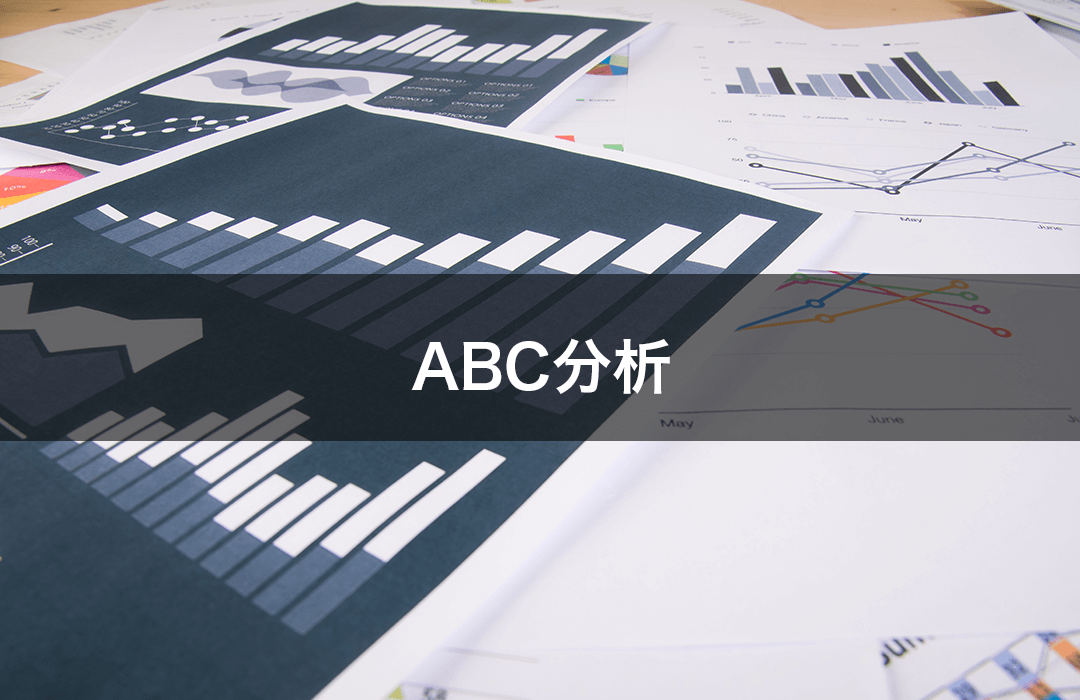 在庫アイテムをA、B、Cの3つのカテゴリに分類し、売上高や利益などの基準に基づいて優先度を付けます。Aクラスは高価値の商品で、厳密な管理が必要です。
在庫アイテムをA、B、Cの3つのカテゴリに分類し、売上高や利益などの基準に基づいて優先度を付けます。Aクラスは高価値の商品で、厳密な管理が必要です。
Bクラスは中間的な価値で、Cクラスは低価値の商品です。
この分析を通じて、重要なアイテムに重点を置くことができます。
ABC分析についての詳細は、こちらからご覧いただけます。
⑦先入れ先出し
 在庫管理の手法の一つで、
在庫管理の手法の一つで、
最初に入庫した商品や資材が最初に出庫される原則を指します。
これは、商品の鮮度や賞味期限が関係する場合や、
商品の劣化を避けるために重要なアプローチとなります。
先入れ先出しについての詳細は、こちらからご覧いただけます。
⑧在庫管理システムの活用
 在庫管理ソフトウェアやシステムを活用して、
在庫管理ソフトウェアやシステムを活用して、
在庫のトラッキング、注文処理、需要予測などを自動化することで、
人為的なミスを減少させ、効率を向上させることができます。
在庫管理システムについての詳細は、こちらからご覧いただけます。
⑨在庫回転率

在庫回転率は、企業が一定期間内に在庫をどれだけ効率的に
回転させているかを示す指標です。
在庫回転率は、売上高と平均在庫を用いて計算され、
在庫管理の効率性を評価するのに役立ちます。
在庫回転率の解釈には注意が必要で、
業界や企業の特性によって適切な回転率が異なります。
例えば、商品の性質や需要の変動が大きい業界では、
高い在庫回転率が求められることがあります。
一方、高額な商品や特定の季節に需要が集中する商品を扱う場合、
適度な在庫を保持することが必要であり、
そのための低い在庫回転率が適切とされることもあります。
在庫管理のメリット

在庫管理によるメリットはいくつもあります。
①生産性が向上する
在庫管理を徹底することで、生産性が向上します。
商品を探すなど、ムダな時間が減るので、作業時間の短縮につながります。
②余剰在庫が減る
「在庫が無いと不安」
過剰在庫の原因は、ここにあります。
ではなぜ、過剰在庫が起きるのか。
それは在庫を理解していないからです。
正しい在庫管理をすることで、 余剰在庫は減少します。
③スペースができる
在庫管理の手法として、置き場所を決める方法があります。
これをすることで、例えばAという商品が、
いろいろなロケーションにあった場合と、
Aのロケーションを1つにまとめるのとでは、
やはり1つにまとめたほうが、倉庫内のスペースは確保できますよね。
④欠品の減少
これもスペースの確保と似ていますが、
ものの置き場所を決めることで、
探しているものが、他のもので埋まることを防ぎます。
またこれは生産性の向上にも繋がります。
⑤品質の安定
在庫の劣化は仕入れの段階で始まります。
長期保管となると、倉庫という広い現場でも
ホコリがかぶるなどで、異物混入の可能性もあります。
在庫管理により、出し入れを繰り返すことで
劣化などを防ぐことができます。
⑥管理費が減る
在庫管理は、コストがかかるものです。
在庫管理をする際に、まず出てくるものが、
WMS(倉庫管理システム)です。
そのシステムの導入費用や、維持費などがありますが、
結果的に在庫管理がうまくいくと、
生産性の向上に伴う人件費の削減や光熱費や減価償却費などの削減に繋がります。
在庫管理のお悩みは、WMS「クラウドトーマス」にお任せください!
詳細を知るには、【無料】の資料ダウンロードがおすすめです▼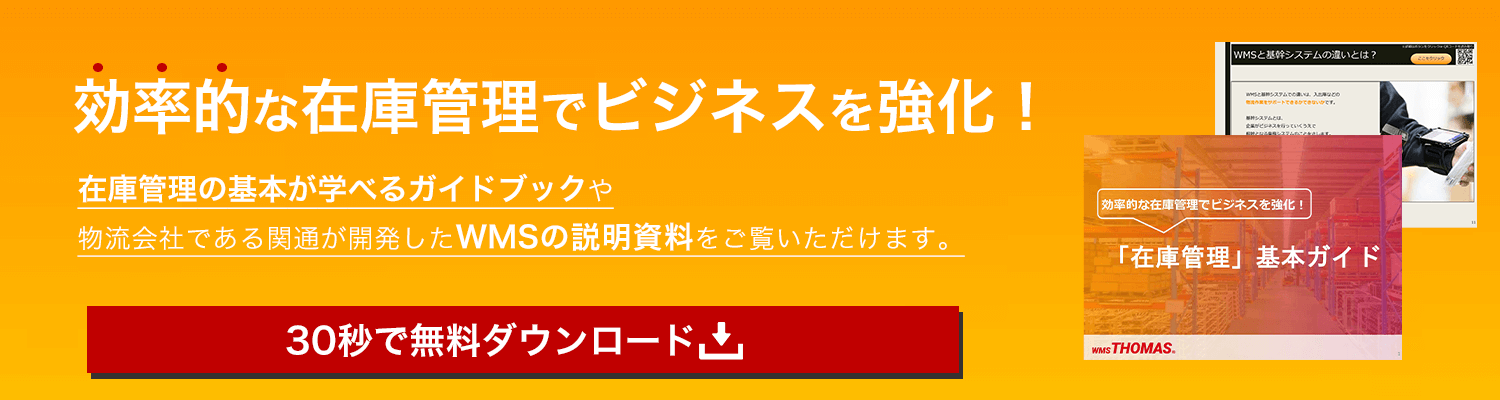
⑦今後の需要予測ができる
在庫を細かく回すことで、市場の動きに敏感になれます。
需要の予測を元に発注をすれば、計画的に生産を進めることができます。
⑧手間やミスが減る
エクセルでも、入出庫といった在庫管理残数を把握することは可能です。
ですが、在庫管理を在庫管理ノートや紙、Excelなどで行うと、ミスも起こりがちで手間もかかります。
在庫管理システムでは、充実した在庫管理機能でシステム上で
すべの在庫を管理することができます。入出庫履歴もリアルタイムで確認することができ、見やすい在庫表でミスや手間が格段と減ります。
在庫管理システム

在庫管理システムは、企業が効率的に在庫を管理するための重要なツールです。
このシステムは、製品の入出庫や在庫レベルをリアルタイムで追跡し、正確な在庫情報を提供します。
また、需要予測や在庫の最適化、棚卸し作業の自動化などの機能を備えています。
これにより、在庫の過不足を防ぎ、業務効率を向上させます。さらに、クラウドベースのシステムでは、複数の場所からアクセスできるため、リモート作業や複数拠点での在庫管理も容易です。
しかし、システムの導入にはコストや学習曲線が伴います。
企業は自社のニーズに合ったシステムを選定し、従業員のトレーニングやシステムの最適化に努めることが重要です。
在庫管理システム導入 のメリット

在庫管理システムの導入には、次のようなメリットがあります。
①場所を気にせずどこでも利用できる
クラウド型のシステムは、インターネットに接続さえできれば、
場所を選ばずどこでも利用することが可能です。
倉庫間での運用が可能なので、繁忙期なども安心です。
②コスト削減
wifi工事やパッケージライセンスの購入が不要になるので、
コストを抑えることができます。
このようなメリットがある点で、クラウド型の在庫管理システムを選ぶ人が増えてきています。
③作業品質の向上
在庫管理システムを導入することで、在庫管理は格段にレベルが上がります。
在庫管理システムにより、人間の手作業によるエラーが減ります。
バーコードスキャンや自動データ入力によって、
正確な在庫情報を保持できるため作業品質が向上します。
在庫管理システムを導入は、作業ミスを減らせる・生産性があがるなど、
会社にとってメリットになることがたくさんあります。
在庫管理システム導入のデメリット
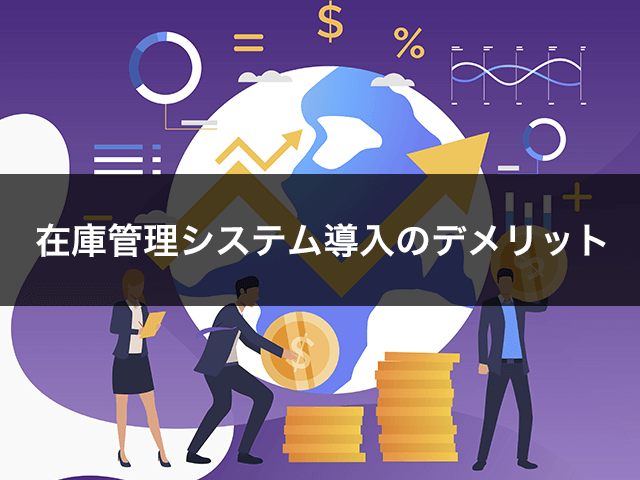
在庫管理システムの導入には、メリットがある反面デメリットもあります。
新しいシステムを導入するには、ソフトウェアライセンスやハードウェアの購入、
カスタマイズや導入にかかるコンサルティング費用などがかかります。
特に中小企業など、予算に余裕のない場合は負担となる可能性があります。
また、システムを導入した後も、運用やメンテナンスに人的リソースが必要です。
データの入力、更新、バックアップ、トラブルシューティングなどを行うため、
追加のコストがかかる場合があります。
これらのデメリットを考慮して、在庫管理システムの導入を検討する際には、
利点とのバランスを考え、慎重な判断が必要です。
適切なシステムを選定し、十分な計画と対策を講じることが重要です。
在庫管理システムを検討されている方は、「クラウドトーマス」にお任せください!
詳細を知るには、【無料】の資料ダウンロードがおすすめです。
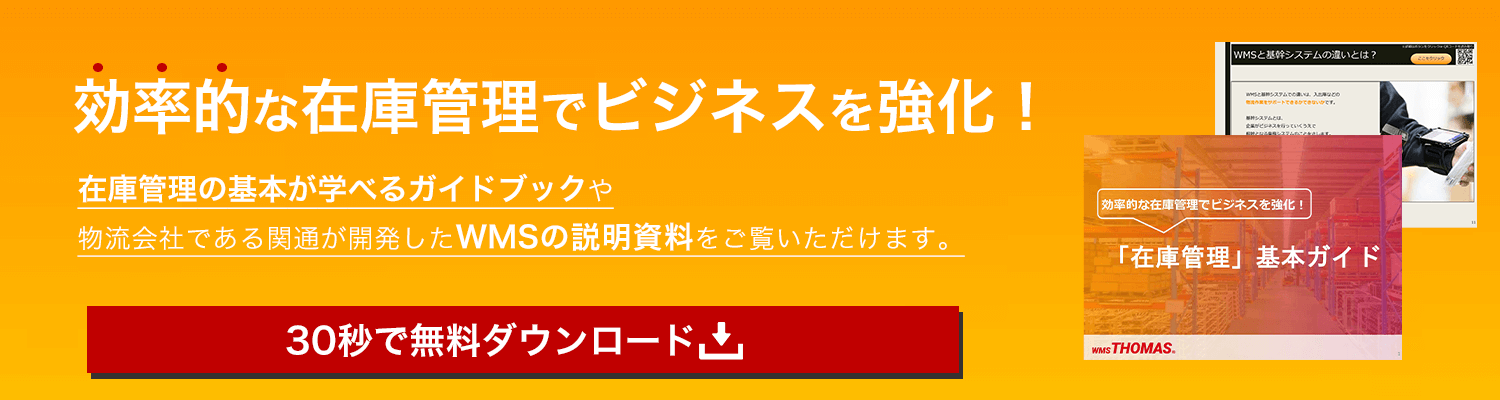
在庫管理システム活用のポイント
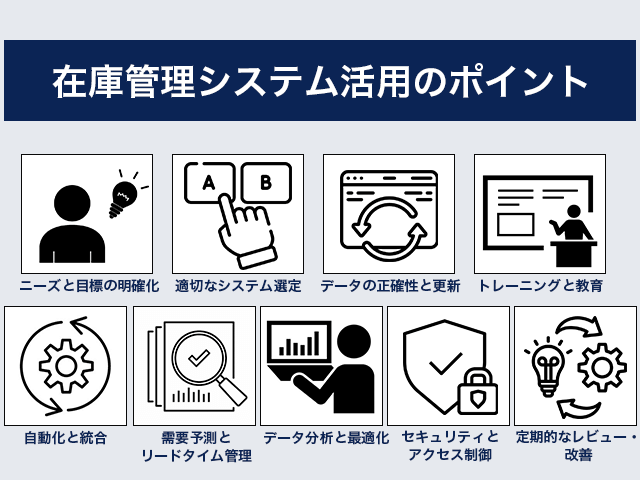
在庫管理システムは、在庫の追跡、管理、予測などを
効率的に行うための強力なツールです。
以下に、在庫管理システムを活用する際のポイントをいくつかご紹介します。
①ニーズと目標の明確化
在庫管理システムを導入する前に、
自社のニーズと目標を明確に理解することが重要です。
需要予測、在庫最適化、ピッキング効率の向上など、どのような課題を解決したいかを把握することが重要です。
②適切なシステムの選定
市場にはさまざまな在庫管理システムが存在します。
クラウドベースのシステムやオンプレミスのシステムなど、選択肢を比較検討し、
自社の規模や業種に合ったシステムを選定しましょう。
③データの正確性と更新
誤ったデータが在庫管理システムに入力されると、効果的な管理が難しくなるため、
在庫数、商品の情報、ロケーションなどのデータを
正確かつ定期的に更新しましょう。
④トレーニングと教育
従業員に向けた、 在庫管理システムの機能や操作方法を理解するための
トレーニングを実施しましょう。
適切なトレーニングを受けることで、システムを最大限に活用できます。
⑤自動化と統合
他のビジネスプロセスと在庫管理システムを統合することで、
自動化されたフローを構築できます。
発注、注文処理、リードタイムの管理などを統合することで、
人の手によって行われる作業の削減を行い、ヒューマンエラーを最小限に抑えます。
⑥需要予測とリードタイム管理
需要予測やリードタイムのデータをシステムに統合し、
これらの要因に基づいて在庫を適切に調整します。
需要の変動やサプライヤーの遅延に対応するための戦略を構築します。
⑦データ分析と最適化
在庫管理システムが提供するデータを分析し、
在庫の最適な水準や発注のタイミングを見極めることが重要です。
過去の売上データやトレンドを活用して、最適な戦略を見つけましょう。
⑧セキュリティとアクセス制御
在庫データは機密性が高いことがあります。
適切なセキュリティ対策を講じ、
必要な人々だけがアクセスできるようなアクセス制御を確保します。
⑨定期的なレビューと改善
在庫管理システムの効果を定期的に評価し、必要に応じて改善を行います。
ビジネスの成長や変化に合わせてシステムを最適化していくことが重要です。
在庫管理システムの活用は、効率的な在庫管理を実現するための鍵です。
しかし、システム導入前に計画的な段階を踏むことが成功のポイントです。
まとめ
このように、在庫管理はものを売る企業にとって、
とてつもなく大事なものです。
これをないがしろにすると、企業としての信頼を崩してしまう可能性もあります。
それぐらい大事な在庫管理、ぜひ一度自社で見直してみてはいかがでしょうか?
・PDCAを回すことも、在庫管理の1つである
・在庫管理でもっとも大事なことは、計画を立てること
・在庫管理のメリットで特に大きなものは、「生産性の向上」である
・在庫管理を効率よくするためにはシステムを入れることがオススメ
在庫管理をより正確かつスムーズに業務化できるシステムについてこちらの記事もぜひご覧ください。
▼在庫管理システムについて詳しくはこちら
在庫管理システムとは|在庫管理システムによる物流現場の課題解決
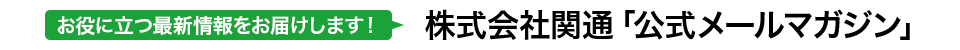
年間700万個出荷の物流を扱う関通が日々現場で蓄積している、「すぐマネできる」改善ノウハウをご紹介しています。